慢性痛と血糖値の関連性について
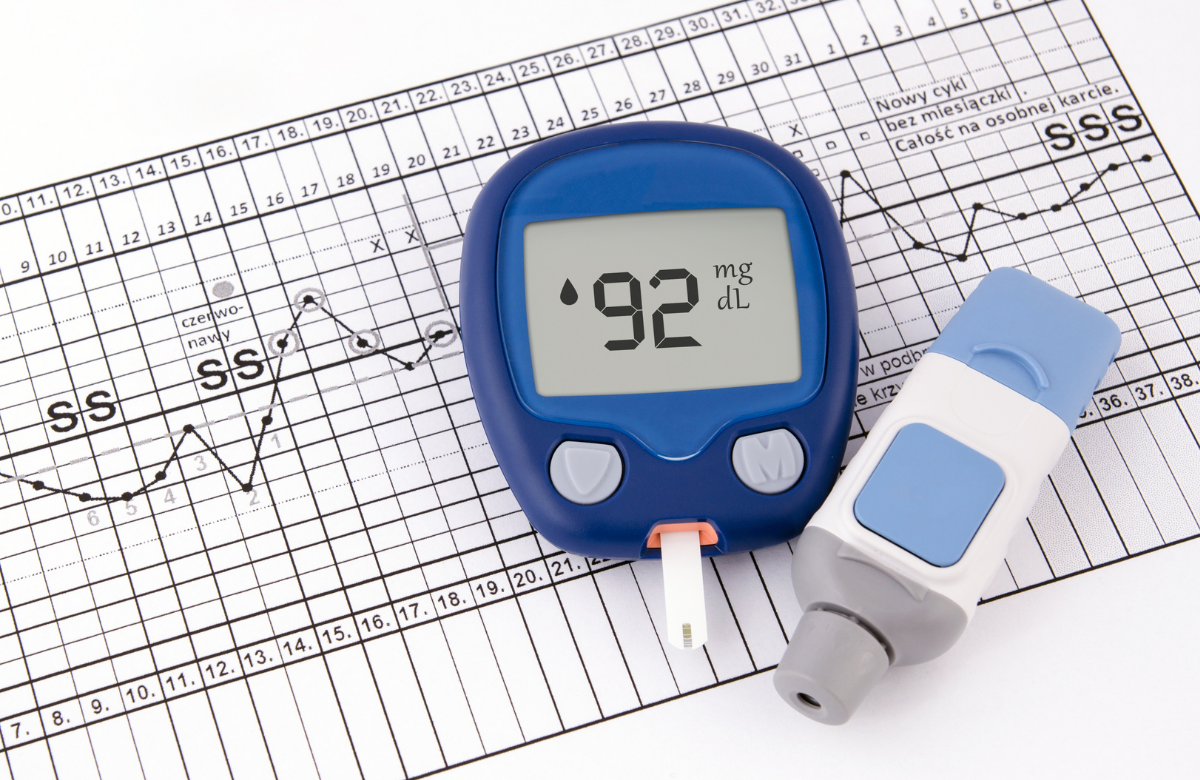
血糖値の乱れが「慢性痛」に?その関係を4つの視点で解説します
こんにちは、ゆらぎ健康調整院の矢ヶ崎です。
今回は「血糖値の乱れ」と「慢性痛」の関係についてご説明します。
血糖値の問題というと、「糖尿病」だけが注目されがちですが、実はそれだけではありません。
血糖値の乱れは、慢性的な痛みやコリ、しびれなどの不調と深い関係があることが、近年の研究で明らかになってきています。
「何をしても痛みが取れない」「整体やマッサージに通っても元に戻る」
そんな方こそ、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
血糖値の乱れが慢性痛につながる4つのポイント
① 末梢血流の低下(筋肉・神経の酸欠)
血糖値が高くなると、血液が“ドロドロ”になりやすくなります。
その結果、細い血管への血流が悪くなり、筋肉や神経への酸素供給が不足してしまいます。
-
筋肉は酸素不足で硬くなり、コリや痛みが発生
-
神経も酸素が足りずに過敏になり、痛みを感じやすくなる
-
ブラジキニンなどの“痛みを誘発する物質”が増える
結果:組織が酸欠状態になると、わずかな刺激でも痛みを強く感じる「過敏な身体」になってしまいます。
② 炎症反応の慢性化(全身の微小炎症)
血糖値が高い状態が続くと、体内では目に見えない「小さな炎症」があちこちで慢性的に起こるようになります。
-
血管・筋肉・関節などに微細な炎症が常に存在
-
筋膜や関節の動きが悪くなり、痛みを引き起こす
-
神経にも炎症が及び、「しびれ」や「ジンジン感」が出現
結果:気づかないうちに進行する“全身の静かな炎症”が、慢性的な痛みの温床となります。
③ 神経への直接的ダメージ(神経障害性疼痛)
高血糖状態が長期間続くと、神経そのものがダメージを受けてしまいます。
-
神経細胞が直接傷つき、機能が乱れる
-
神経を保護している「ミエリン鞘(しょう)」が壊れる
-
自律神経も影響を受け、痛みの感覚が乱れる
結果:「ピリピリ」「ジンジン」といった特有の神経痛が起こりやすくなり、一般的な痛み止めも効きにくくなってしまいます。
④ 組織の糖化(AGEs)による硬化と痛み
血糖値が高い状態では、「糖化」という現象が体内で進行します。
これは、タンパク質が余分な糖と結びつき、組織が硬く劣化してしまう反応です(いわば“体のカラメル化”)。
-
筋肉や腱、靭帯が硬くなって、柔軟性が低下
-
関節周囲の組織が硬化し、可動域が狭くなる
-
回復力が落ち、治りにくい体質へ
結果:体の各部が少しずつ硬くなり、動きに制限が出て、痛みが慢性化していきます。
まとめ
血糖値の乱れは、単に糖尿病のリスクだけでなく、痛みや不調の根本原因としても深く関わっています。
慢性痛を本当に改善するためには、筋肉や骨格のバランスだけでなく、体の内側=血糖と血流の環境を整えることがとても大切です。
当院では、こうした体内環境も含めた総合的な視点からの施術とアドバイスを行っています。
「食後に腰や脚が痛くなる」「甘いものを食べた後に身体が重くなる」など、血糖と関係がありそうな症状がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
次回以降は、今回ご紹介した①〜④の項目について、さらに詳しく解説していきます。
どうぞお楽しみに。
伊那市・上伊那周辺で腰痛・坐骨神経痛にお悩みなら
-腰痛・坐骨神経痛専門- 「ゆらぎ健康調整院」にご相談ください!